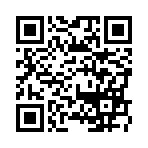2010年04月24日
小論文 「商業立国 日本」【1.本当の「商業」はどこへ】
「100年後にむけての日本又は日本人はどうあるべきか」懸賞論文 応募作
【1.本当の「商業」はどこへ】
「商業立国 日本」
筑波大学国際総合学類3年 山本泰弘
筑波大学国際総合学類3年 山本泰弘
【1.本当の「商業」はどこへ】
「商業」とは何か。これは幼い頃より商家に生まれ育ち、社会科・時事問題に強い関心を持って学生生活を送ってきた私自身が、現在大学生となって疑問を抱くに至った問いである。
私の実家は地方小都市の旧中心商店街で衣料品・雑貨店を営んでいる。家族と数名の店員による経営で、元日と店卸し以外年中無休、時間外のお客さんにも店を開けて対応する、まさに“商店街のお店”であり続けてきた。店の歴史からすれば私の記憶している時代はわずかだが、なじみの店員さんが入れ替わり、店舗が建て替わり、商店街がだんだんと衰退していく中でも店の本質は変わらずそこに在り続けている。お店のひともお客さんも笑顔のやり取りがあり、お店のひとはどうにかお客さんに役立とうという思いで仕事をしていた。働く動機は、お金よりむしろそこにあった。
私はそのような家で、小さい頃から手伝いに立ちつつ「商い・商売」とはそのようなもの――お客さんに役立ち、お客さんの評価によって支えられる――と信じてきたが、実際の世の中や人々を支配している考え方はそうではないことがわかってきた。
進学で大学のある当地にやってきてからの生活は、私の心に培われてきた「商い・商売」の本質を逸脱する場面の連続である。大学関係者を相手にするいわゆる“地元業者”は固定客層があるのをいいことに利益に胡坐をかいているし、学生はマニュアル的対応で事が済むアルバイトに時間を費やして省みない。もちろん全てをひとくくりにはできないが、単刀直入に言えば仕事の動機として「カネ」が先立っているのである。
これは個人の生活上の事柄にとどまらない。日本の社会に目を転じれば、“自らより消費者や世の中の役に立つために”という精神をないがしろにした商売があふれている。商店街に代わって小売の主役の座を極めたコンビニ・ファストフードチェーン店などのアルバイト中心・マニュアル主義の運営は言うに及ばず、今やその例外を見つけることのほうが難しい。また当地で特に顕著な例があるのが、政治的な利益誘導によって住民に不要な建築物が造られるという事態である。建設業者も、政治家も“住民・地域よりも自らのため”の仕事をした帰結と言える。
さらに視野を広げれば、現代の経済・社会・政治に共通して“広く一般の人々や世の中の役に立つ=公益に資する”という方針が欠落していることが浮き彫りになる。経済的に利益の発生することに対して無秩序に関与する世の中では、資源収奪のための環境破壊が起こり、安い製品を作るための労働力搾取が横行し、さらには軍需産業に多額の利益が発生することを見越して戦争が推進されたりする。
そしてこれらはいずれも、他ならぬ日本にも当てはまる事態なのである。
[【2.日本伝統の商業倫理】へ]
私の実家は地方小都市の旧中心商店街で衣料品・雑貨店を営んでいる。家族と数名の店員による経営で、元日と店卸し以外年中無休、時間外のお客さんにも店を開けて対応する、まさに“商店街のお店”であり続けてきた。店の歴史からすれば私の記憶している時代はわずかだが、なじみの店員さんが入れ替わり、店舗が建て替わり、商店街がだんだんと衰退していく中でも店の本質は変わらずそこに在り続けている。お店のひともお客さんも笑顔のやり取りがあり、お店のひとはどうにかお客さんに役立とうという思いで仕事をしていた。働く動機は、お金よりむしろそこにあった。
私はそのような家で、小さい頃から手伝いに立ちつつ「商い・商売」とはそのようなもの――お客さんに役立ち、お客さんの評価によって支えられる――と信じてきたが、実際の世の中や人々を支配している考え方はそうではないことがわかってきた。
進学で大学のある当地にやってきてからの生活は、私の心に培われてきた「商い・商売」の本質を逸脱する場面の連続である。大学関係者を相手にするいわゆる“地元業者”は固定客層があるのをいいことに利益に胡坐をかいているし、学生はマニュアル的対応で事が済むアルバイトに時間を費やして省みない。もちろん全てをひとくくりにはできないが、単刀直入に言えば仕事の動機として「カネ」が先立っているのである。
これは個人の生活上の事柄にとどまらない。日本の社会に目を転じれば、“自らより消費者や世の中の役に立つために”という精神をないがしろにした商売があふれている。商店街に代わって小売の主役の座を極めたコンビニ・ファストフードチェーン店などのアルバイト中心・マニュアル主義の運営は言うに及ばず、今やその例外を見つけることのほうが難しい。また当地で特に顕著な例があるのが、政治的な利益誘導によって住民に不要な建築物が造られるという事態である。建設業者も、政治家も“住民・地域よりも自らのため”の仕事をした帰結と言える。
さらに視野を広げれば、現代の経済・社会・政治に共通して“広く一般の人々や世の中の役に立つ=公益に資する”という方針が欠落していることが浮き彫りになる。経済的に利益の発生することに対して無秩序に関与する世の中では、資源収奪のための環境破壊が起こり、安い製品を作るための労働力搾取が横行し、さらには軍需産業に多額の利益が発生することを見越して戦争が推進されたりする。
そしてこれらはいずれも、他ならぬ日本にも当てはまる事態なのである。
[【2.日本伝統の商業倫理】へ]
2012-11 プライマリ・ケア+αの広場「健こう民館」構想
2014年12月:復興庁主催政策コンテスト「REVIVE JAPAN CUP」入選・決選進出!
地球温暖化対策の中期目標に対するコメント(麻生政権時)
小論文「『市民金融』で躍動するまちづくりを目指す」
小論文 「商業立国 日本」【3.三つの提言】
小論文 「商業立国 日本」【2.日本伝統の商業倫理】
2014年12月:復興庁主催政策コンテスト「REVIVE JAPAN CUP」入選・決選進出!
地球温暖化対策の中期目標に対するコメント(麻生政権時)
小論文「『市民金融』で躍動するまちづくりを目指す」
小論文 「商業立国 日本」【3.三つの提言】
小論文 「商業立国 日本」【2.日本伝統の商業倫理】
Posted by 山本泰弘 at 00:00│Comments(0)
│【応募・投稿】
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。