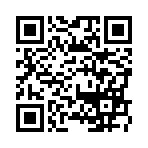2010年04月05日
【応募・投稿】
・2012年11月 GEヘルシーマジネーション大賞「一人ひとりの健康を身近で支える医療
~ 少子高齢社会におけるプライマリ・ケアのあり方とは?」 入選・決選進出
「プライマリ・ケア+αの広場『健こう民館』構想」
・2012年10月 ヤンマー学生懸賞「進化する農へ挑戦」応募 「『米商品券』流通政策」
・2012年10月 一般社団法人 商工総合研究所 中小企業懸賞論文「わが国における起業家教育」応募
「商売・起業の『基本』の帰」
・2012年9月 野村総合研究所 NRI学生小論文コンテスト
「自分たちの子ども世代に創り伝えたい社会~あるべき社会の姿と私たちの挑戦」応募・大賞
「政経社会系教育重点校『スーパーソーシャルハイスクール」
・2011年9月 社団法人 日本経済調査協議会 50周年記念懸賞論文「今こそ日本の進路を問う」応募
「今こそ日本の進路を問う ~『真なる豊かさ』に立ち返るとき~」
・2010年9月 社団法人 建設コンサルタンツ協会 2010年度懸賞論文「低炭素社会にふさわしいまちづくり」応募・佳作入賞 「『市民金融』で躍動するまちづくりを目指す」
・2009年5月、内閣官房「地球温暖化対策の中期目標に対するパブリックコメント」投稿
・2008年10月、社団法人日本プロジェクト産業協議会 懸賞論文「100年後にむけての日本又は日本人はどうあるべきか」応募 「商業立国 日本」
・2008年、第4回出版甲子園 応募 第3次選考進出 「授業じゃ聞けない環境学」
~ 少子高齢社会におけるプライマリ・ケアのあり方とは?」 入選・決選進出
「プライマリ・ケア+αの広場『健こう民館』構想」
・2012年10月 ヤンマー学生懸賞「進化する農へ挑戦」応募 「『米商品券』流通政策」
・2012年10月 一般社団法人 商工総合研究所 中小企業懸賞論文「わが国における起業家教育」応募
「商売・起業の『基本』の帰」
・2012年9月 野村総合研究所 NRI学生小論文コンテスト
「自分たちの子ども世代に創り伝えたい社会~あるべき社会の姿と私たちの挑戦」応募・大賞
「政経社会系教育重点校『スーパーソーシャルハイスクール」
・2011年9月 社団法人 日本経済調査協議会 50周年記念懸賞論文「今こそ日本の進路を問う」応募
「今こそ日本の進路を問う ~『真なる豊かさ』に立ち返るとき~」
・2010年9月 社団法人 建設コンサルタンツ協会 2010年度懸賞論文「低炭素社会にふさわしいまちづくり」応募・佳作入賞 「『市民金融』で躍動するまちづくりを目指す」
・2009年5月、内閣官房「地球温暖化対策の中期目標に対するパブリックコメント」投稿
・2008年10月、社団法人日本プロジェクト産業協議会 懸賞論文「100年後にむけての日本又は日本人はどうあるべきか」応募 「商業立国 日本」
・2008年、第4回出版甲子園 応募 第3次選考進出 「授業じゃ聞けない環境学」
2010年04月24日
2010年04月24日
2010年04月24日
2010年04月24日
小論文「『市民金融』で躍動するまちづくりを目指す」
社団法人建設コンサルタンツ協会主催 懸賞論文「低炭素社会にふさわしいまちづくり」(2010年9月末締め切り) 応募作
「市民金融」で躍動するまちづくりを目指す
山本泰弘(筑波大学大学院 人文社会科学研究科 科目等履修生)
続きを読む山本泰弘(筑波大学大学院 人文社会科学研究科 科目等履修生)
2010年04月30日
地球温暖化対策の中期目標に対するコメント(麻生政権時)
2009/05/16
筑波大学 3Ecafeプロジェクトチーム
「3Ecafeプロジェクトチーム」は、筑波大学の学生有志による組織で、筑波大学が主唱する「つくば3E(環境Environment、エネルギー Energy、経済Economy)フォーラム宣言」の趣旨に同調し低炭素社会・環境都市の実現に向けた提言活動を行っています。
≪3Ecafeプロジェクトチームによる意見≫
(1)我が国の温室効果ガスの中期目標(2020年)は、どの程度の排出量とすべきか
私たちは、「1990年比-15%」(シナリオ⑤)を支持する。その理由は以下のとおりである。
①国立環境研究所の研究結果として発表されている以下の点を、特に重視すべきであること。
・「1990年比-15%」の場合でも持続的な経済成長は確保され、シナリオ①「長期需給見通し努力継続」の場合の実質GDP成長がわずか7か月遅れで達成される。
・低炭素社会は科学的に必至であり、特に社会・産業界へその方針を明確に示すシグナルを与える目標設定が必要である。
②国際交渉上での以下の要求を満たす必要があること。
温室効果ガス削減の国際的枠組みに対する現在の日本の根本的主張に、「主要な温室効果ガス排出国のすべてが参加する枠組みを作る」というものがある。同時にアメリカは、中国・インドを含めることを枠組みへの参加条件としており、他方中国をはじめとする新興国・発展途上国の多くは先進国の大幅排出削減(-25~-40%)を枠組みへの参加条件としている。よって「先進国全体で1990年比-25%」の要求が課せられる可能性が高い。(そしてその場合、一律の数値目標を要求するEUとの妥協が必要となる。シナリオ②・④での妥協は非常に困難と考えられる。)
③それぞれのシナリオによる経済への影響が、GDPに大きく依存して算出されていること。
「1990年比-15%」のような積極的な削減目標を設定することによるGDPの押し下げ効果を問題視する意見が多いが、経済発展をGDPのみに依存して測り続けることは危険である。GDPは、非効率な活動もプラスとみなされる 経済の「規模」を表す指標だからである。GDP上ではマイナスともなりえる経済の「質・効率」が重視される21世紀において、「GDPに縛られない経済成長」を目指すべきである。
(※詳細な主張・提案→(3)その他、2020 年頃に向けた我が国の地球温暖化対策に関する意見Ⅰ)
④国際金融市場における「社会的責任投資」概念の世界的拡大が予測されること。
2006年、国際連合は「国際連合責任投資原則」を提唱し、環境・社会・コーポレートガヴァナンスへの配慮・貢献を評価した資金運用を行うことを世界の機関投資家に呼びかけた。この原則に各国の政府基金・公的年金の運用責任者などが署名しており、今後この観点に基づく資産運用は世界的潮流になると予測される。国内投資ポテンシャルが逓減する日本が海外からの投資をより受け入れるためには、国として低炭素社会への転換を指揮する目標設定が必要と考えられる。
⑤以下の観点による「世代間の公正」を確保すること。
・中期目標検討委員会の報告によると、どのシナリオを採った場合でも2050年-60%~-80%の目標は達成できるとされているが、2050年までの期間で削減のための負担を平準化すべきである。
・あくまで現状の構造に基づいた保守的な目標設定を行うことで、将来の日本が得られる環境関連分野での優位とそれに基づいた国民生活の豊かさ・日本経済の安定性・国際的地位などを失うことは、著しく不公正である。
日本が今 社会・産業の低炭素社会対応を開始せず、環境関連産業の育成支援・雇用創出と環境分野の人材育成などに着手しなければ、国際競争力を著しく損なうばかりか有能な人材・企業の国外流出を招く結果となることが十分考えられる。
⑥現在限定的に認定されているCDM:クリーン開発メカニズム・JI:共同実施 の拡大を伴うことで、排出権の上乗せが可能であること。
日本にとって有利と思われるCDM・JIは、現在国の削減量に算入される上限が厳しく設定され、その認定のプロセスも煩雑である。日本は「1990年比 -15%」の目標を設定すると同時に、「ポスト京都」の枠組みにおいてCDM・JIの拡大を主張すべきであり、その目標設定によって主張に説得力が生まれると考えられる。
(※詳細な主張・提案→(3)その他、2020 年頃に向けた我が国の地球温暖化対策に関する意見Ⅱ)
(2)その中期目標の実現に向けて、どのような政策を実施すべきか
具体的な政策については、基本的に中期目標検討委員会・国立環境研究所の提示する「1990年比-15%」シナリオ(シナリオ⑤)にて提案されているものを支持する。
ただし、「1990年比-25%」シナリオ(シナリオ⑥)にのみ示されている「炭素への価格付け政策」、特に炭素税は目標値に関わらず実施すべきである。その場合、消費税のように流通部門より最終消費者により割高な負担を求めるべきである。
(3)その他、2020年頃に向けた我が国の地球温暖化対策に関する意見
Ⅰ・経済指標の「GDP」一極集中からの脱却――「効率性」を重視した代替経済指標の導入
― 日本の目指す「低炭素社会」の経済で重要視すべきなのは、その「規模」ではなく「質」である。あらゆる資源・生産物をいかに効率的に利用して生産性を向上させるかが問われる21世紀において、不必要な資源投入・生産物消費の規模をも反映して算出するGDPは、経済指標としての意味をなしえない。投入された資源・生産物が非効率に利用されてもGDPの増加として表されるからである。逆に効率化により資源投入量・生産物消費量を削減すれば、それはGDP減少と見なされる。
未来志向の政策目標に用いられる経済指標が20世紀的なもののみであることは許されない。これまで経済成長の指標をGDPのみに依存してきたことを見直し、「GDPに縛られない経済成長」を提唱すべきである。
GDPに代わる指標としては、「グリーンGDP」が一部で取りざたされているが、数値化の対象を「自然資源の減耗」・「環境に関する外部不経済」に限定している点で不十分である。自然環境に直接正負の影響を与えない経済の効率化が反映されていない。
資源投入量・生産物消費量を圧縮しつつ生産性を向上させる――これは、市中の民間企業、政府機関、もしくは家計などの単位で個別的に実施されていることであるが、その効果を統合した指標が不在である。そこで、新たな指標を確立・採用し、日本として主張することを求めたい。
Ⅱ・国際交渉における日本の戦略
―(1)⑥で述べたように、日本はCDM・JIを可能な限り有効活用できる仕組みの設定を主張すべきであると考える。ポスト京都の国際交渉では、認定上限の拡大・認定プロセスの円滑化を求めるとともに、京都メカニズムによって生まれる利益から気候変動適応基金に拠出される資金の割合を上げることを提案することで、発展途上国の賛同を得られるのではないか。
3Ecafeプロジェクトチーム(学生有志団体)
担当者:筑波大学国際総合学類4年 山本泰弘
筑波大学 3Ecafeプロジェクトチーム
地球温暖化対策の中期目標に対するコメント
「3Ecafeプロジェクトチーム」は、筑波大学の学生有志による組織で、筑波大学が主唱する「つくば3E(環境Environment、エネルギー Energy、経済Economy)フォーラム宣言」の趣旨に同調し低炭素社会・環境都市の実現に向けた提言活動を行っています。
筑波大学 つくば3Eフォーラム http://www.sakura.cc.tsukuba.ac.jp/~eeeforum/
3Ecafe HP http://t3ecafe.me.land.to/
3Ecafe ブログ http://t3ecafe.tsukuba.ch/
3Ecafe HP http://t3ecafe.me.land.to/
3Ecafe ブログ http://t3ecafe.tsukuba.ch/
≪3Ecafeプロジェクトチームによる意見≫
(1)我が国の温室効果ガスの中期目標(2020年)は、どの程度の排出量とすべきか
私たちは、「1990年比-15%」(シナリオ⑤)を支持する。その理由は以下のとおりである。
①国立環境研究所の研究結果として発表されている以下の点を、特に重視すべきであること。
・「1990年比-15%」の場合でも持続的な経済成長は確保され、シナリオ①「長期需給見通し努力継続」の場合の実質GDP成長がわずか7か月遅れで達成される。
・低炭素社会は科学的に必至であり、特に社会・産業界へその方針を明確に示すシグナルを与える目標設定が必要である。
②国際交渉上での以下の要求を満たす必要があること。
温室効果ガス削減の国際的枠組みに対する現在の日本の根本的主張に、「主要な温室効果ガス排出国のすべてが参加する枠組みを作る」というものがある。同時にアメリカは、中国・インドを含めることを枠組みへの参加条件としており、他方中国をはじめとする新興国・発展途上国の多くは先進国の大幅排出削減(-25~-40%)を枠組みへの参加条件としている。よって「先進国全体で1990年比-25%」の要求が課せられる可能性が高い。(そしてその場合、一律の数値目標を要求するEUとの妥協が必要となる。シナリオ②・④での妥協は非常に困難と考えられる。)
③それぞれのシナリオによる経済への影響が、GDPに大きく依存して算出されていること。
「1990年比-15%」のような積極的な削減目標を設定することによるGDPの押し下げ効果を問題視する意見が多いが、経済発展をGDPのみに依存して測り続けることは危険である。GDPは、非効率な活動もプラスとみなされる 経済の「規模」を表す指標だからである。GDP上ではマイナスともなりえる経済の「質・効率」が重視される21世紀において、「GDPに縛られない経済成長」を目指すべきである。
(※詳細な主張・提案→(3)その他、2020 年頃に向けた我が国の地球温暖化対策に関する意見Ⅰ)
④国際金融市場における「社会的責任投資」概念の世界的拡大が予測されること。
2006年、国際連合は「国際連合責任投資原則」を提唱し、環境・社会・コーポレートガヴァナンスへの配慮・貢献を評価した資金運用を行うことを世界の機関投資家に呼びかけた。この原則に各国の政府基金・公的年金の運用責任者などが署名しており、今後この観点に基づく資産運用は世界的潮流になると予測される。国内投資ポテンシャルが逓減する日本が海外からの投資をより受け入れるためには、国として低炭素社会への転換を指揮する目標設定が必要と考えられる。
⑤以下の観点による「世代間の公正」を確保すること。
・中期目標検討委員会の報告によると、どのシナリオを採った場合でも2050年-60%~-80%の目標は達成できるとされているが、2050年までの期間で削減のための負担を平準化すべきである。
・あくまで現状の構造に基づいた保守的な目標設定を行うことで、将来の日本が得られる環境関連分野での優位とそれに基づいた国民生活の豊かさ・日本経済の安定性・国際的地位などを失うことは、著しく不公正である。
日本が今 社会・産業の低炭素社会対応を開始せず、環境関連産業の育成支援・雇用創出と環境分野の人材育成などに着手しなければ、国際競争力を著しく損なうばかりか有能な人材・企業の国外流出を招く結果となることが十分考えられる。
⑥現在限定的に認定されているCDM:クリーン開発メカニズム・JI:共同実施 の拡大を伴うことで、排出権の上乗せが可能であること。
日本にとって有利と思われるCDM・JIは、現在国の削減量に算入される上限が厳しく設定され、その認定のプロセスも煩雑である。日本は「1990年比 -15%」の目標を設定すると同時に、「ポスト京都」の枠組みにおいてCDM・JIの拡大を主張すべきであり、その目標設定によって主張に説得力が生まれると考えられる。
(※詳細な主張・提案→(3)その他、2020 年頃に向けた我が国の地球温暖化対策に関する意見Ⅱ)
(2)その中期目標の実現に向けて、どのような政策を実施すべきか
具体的な政策については、基本的に中期目標検討委員会・国立環境研究所の提示する「1990年比-15%」シナリオ(シナリオ⑤)にて提案されているものを支持する。
ただし、「1990年比-25%」シナリオ(シナリオ⑥)にのみ示されている「炭素への価格付け政策」、特に炭素税は目標値に関わらず実施すべきである。その場合、消費税のように流通部門より最終消費者により割高な負担を求めるべきである。
(3)その他、2020年頃に向けた我が国の地球温暖化対策に関する意見
Ⅰ・経済指標の「GDP」一極集中からの脱却――「効率性」を重視した代替経済指標の導入
― 日本の目指す「低炭素社会」の経済で重要視すべきなのは、その「規模」ではなく「質」である。あらゆる資源・生産物をいかに効率的に利用して生産性を向上させるかが問われる21世紀において、不必要な資源投入・生産物消費の規模をも反映して算出するGDPは、経済指標としての意味をなしえない。投入された資源・生産物が非効率に利用されてもGDPの増加として表されるからである。逆に効率化により資源投入量・生産物消費量を削減すれば、それはGDP減少と見なされる。
未来志向の政策目標に用いられる経済指標が20世紀的なもののみであることは許されない。これまで経済成長の指標をGDPのみに依存してきたことを見直し、「GDPに縛られない経済成長」を提唱すべきである。
GDPに代わる指標としては、「グリーンGDP」が一部で取りざたされているが、数値化の対象を「自然資源の減耗」・「環境に関する外部不経済」に限定している点で不十分である。自然環境に直接正負の影響を与えない経済の効率化が反映されていない。
資源投入量・生産物消費量を圧縮しつつ生産性を向上させる――これは、市中の民間企業、政府機関、もしくは家計などの単位で個別的に実施されていることであるが、その効果を統合した指標が不在である。そこで、新たな指標を確立・採用し、日本として主張することを求めたい。
Ⅱ・国際交渉における日本の戦略
―(1)⑥で述べたように、日本はCDM・JIを可能な限り有効活用できる仕組みの設定を主張すべきであると考える。ポスト京都の国際交渉では、認定上限の拡大・認定プロセスの円滑化を求めるとともに、京都メカニズムによって生まれる利益から気候変動適応基金に拠出される資金の割合を上げることを提案することで、発展途上国の賛同を得られるのではないか。
3Ecafeプロジェクトチーム(学生有志団体)
担当者:筑波大学国際総合学類4年 山本泰弘
2014年12月21日
2014年12月:復興庁主催政策コンテスト「REVIVE JAPAN CUP」入選・決選進出!
僕の政策案「サスラエ!国内留学JAPAN~『国内留学』推進政策~」が、復興庁主催政策コンテスト「REVIVE JAPAN CUP」で入選し、決選プレゼンテーションに進むことになりました!
この案は一目瞭然、国策の「トビタテ!留学JAPAN」の裏をかくものです。
福澤諭吉ら明治の偉人も、幾度とない国内の旅を経て外国へ渡り、国際人となりました。国内の見聞を経た真のグローバル人を育むことに加え、被災地をはじめとした地域振興、内需刺激、復興への関心持続を狙う政策です。
「トビタテ!」政策を補う続編として、実現しましょう`・ω・´
政策決定者につながりのある方、本案をご紹介ください。
※Facebook投稿はこちら
※応募原稿はこちら(Google Drive)。
この案は一目瞭然、国策の「トビタテ!留学JAPAN」の裏をかくものです。
福澤諭吉ら明治の偉人も、幾度とない国内の旅を経て外国へ渡り、国際人となりました。国内の見聞を経た真のグローバル人を育むことに加え、被災地をはじめとした地域振興、内需刺激、復興への関心持続を狙う政策です。
「トビタテ!」政策を補う続編として、実現しましょう`・ω・´
政策決定者につながりのある方、本案をご紹介ください。
※Facebook投稿はこちら
※応募原稿はこちら(Google Drive)。
2014年12月21日
2012-11 プライマリ・ケア+αの広場「健こう民館」構想
2012-11
GEヘルシーマジネーション大賞
一人ひとりの健康を身近で支える医療~少子高齢社会におけるプライマリ・ケアのあり方とは?
1.現状の課題
人々にとって、医療や医療機関とはどのようにとらえられているか。
ほぼすべての人の固定観念にあるのは、「病気・けがの時頼るもの」であろう。「病院」の語が体現するように、不健康の度合いが一線を越えたとき、いわばマイナスを埋め合わせるべくお世話になるのが医療や医療従事者であり、病院という場なのである。
2.医療のポテンシャル
ある程度深いマイナス状態にならないと医療に接しないというのは、人々の生き方と社会全体にとって、極めて大きな損失である。医療はその“埋め合わせ”にとどまらず、健康状態でいくばくかのマイナスを持つ人をプラスへ転じさせたり、わずかなプラスを大きなプラスへ成長させることができるもののはずである。
実際社会には、健康を保ちたい・より健康になりたいと志向する人が数多く存在する。そしてその延長線上には、ただ生きるのではなく、仕事や社会貢献、表現・創作、学びなど、生きがい・ライフワークと言えるもので彩られた味わい深い生き方をしたいとの希望がある。
身体状態のみならず人生のプラスをもたらすサポーターとして、医療が貢献できるのではないか。
3.ニーズ・ウォンツの指摘
「プライマリ・ケア」の代表的な意味として、“地域の人々の健康問題や疾病への総合的対応”が言われる。これは前述の“マイナスに対処する”医療の一面へのニーズであり、これを下地として“プラスをもたらす”ニーズ・ウォンツへも応えることが「プライマリ・ケア」の真の姿となるのではないか。
健康の維持・向上のほか、(病院がその場となっているとも言われる)コミュニティ交流の機会も求められていると言えるし、人生をアクティブに楽しむ要素――仕事、旅行、食や買い物、NPO活動など――へのアクセスも潜在的需要があるのではないか。
「病院」ではない、健康や予防を基盤としつつもアクティブシニア(を中心とする人々)の活動拠点となるようなプライマリ・ケアの広場が求められているのではないか。
4.解決策の提示
その具体像として、プライマリ・ケア広場「健こう民館」を提案する。
ここには医療者がいて疾病対処から予防医療、食や運動へのアドバイスを提供するほか、栄養バランス配慮で1,2人の家庭ではなかなか作れない食事を提供する食堂を備える。そしてアクティブシニアの需要を狙って旅行商品や金融商品を提供するカウンターを設けたり、NPO活動や起業のために使えるシェアオフィススペースを開設したりする。もちろんシニア層に限らず、地域の多様な人々が行き来するキャンパスとするイメージだ。いわゆる“お年寄り”フレームを払拭した、ダイナミックな趣味や経済活動、地域活動の舞台とする。医療はその役者のパフォーマンスをしっかり支える役割を果たす。
5.期待される効果
数値的効果としては、予防や早期発見による医療費削減、消費活動の活発化による経済効果が見込めよう。しかし最も大きいものはQOLの向上だ。これまで“病院”・“お年寄り”という枠で括られその雰囲気に同調せざるを得なかった人が、医療の助けも得てより鮮やかな人生を送れるようになる。プライマリ・ケアの理想像はそこにあるのではないか。
GEヘルシーマジネーション大賞
一人ひとりの健康を身近で支える医療~少子高齢社会におけるプライマリ・ケアのあり方とは?
プライマリ・ケア+αの広場「健こう民館」構想
1.現状の課題
人々にとって、医療や医療機関とはどのようにとらえられているか。
ほぼすべての人の固定観念にあるのは、「病気・けがの時頼るもの」であろう。「病院」の語が体現するように、不健康の度合いが一線を越えたとき、いわばマイナスを埋め合わせるべくお世話になるのが医療や医療従事者であり、病院という場なのである。
2.医療のポテンシャル
ある程度深いマイナス状態にならないと医療に接しないというのは、人々の生き方と社会全体にとって、極めて大きな損失である。医療はその“埋め合わせ”にとどまらず、健康状態でいくばくかのマイナスを持つ人をプラスへ転じさせたり、わずかなプラスを大きなプラスへ成長させることができるもののはずである。
実際社会には、健康を保ちたい・より健康になりたいと志向する人が数多く存在する。そしてその延長線上には、ただ生きるのではなく、仕事や社会貢献、表現・創作、学びなど、生きがい・ライフワークと言えるもので彩られた味わい深い生き方をしたいとの希望がある。
身体状態のみならず人生のプラスをもたらすサポーターとして、医療が貢献できるのではないか。
3.ニーズ・ウォンツの指摘
「プライマリ・ケア」の代表的な意味として、“地域の人々の健康問題や疾病への総合的対応”が言われる。これは前述の“マイナスに対処する”医療の一面へのニーズであり、これを下地として“プラスをもたらす”ニーズ・ウォンツへも応えることが「プライマリ・ケア」の真の姿となるのではないか。
健康の維持・向上のほか、(病院がその場となっているとも言われる)コミュニティ交流の機会も求められていると言えるし、人生をアクティブに楽しむ要素――仕事、旅行、食や買い物、NPO活動など――へのアクセスも潜在的需要があるのではないか。
「病院」ではない、健康や予防を基盤としつつもアクティブシニア(を中心とする人々)の活動拠点となるようなプライマリ・ケアの広場が求められているのではないか。
4.解決策の提示
その具体像として、プライマリ・ケア広場「健こう民館」を提案する。
ここには医療者がいて疾病対処から予防医療、食や運動へのアドバイスを提供するほか、栄養バランス配慮で1,2人の家庭ではなかなか作れない食事を提供する食堂を備える。そしてアクティブシニアの需要を狙って旅行商品や金融商品を提供するカウンターを設けたり、NPO活動や起業のために使えるシェアオフィススペースを開設したりする。もちろんシニア層に限らず、地域の多様な人々が行き来するキャンパスとするイメージだ。いわゆる“お年寄り”フレームを払拭した、ダイナミックな趣味や経済活動、地域活動の舞台とする。医療はその役者のパフォーマンスをしっかり支える役割を果たす。
5.期待される効果
数値的効果としては、予防や早期発見による医療費削減、消費活動の活発化による経済効果が見込めよう。しかし最も大きいものはQOLの向上だ。これまで“病院”・“お年寄り”という枠で括られその雰囲気に同調せざるを得なかった人が、医療の助けも得てより鮮やかな人生を送れるようになる。プライマリ・ケアの理想像はそこにあるのではないか。
終