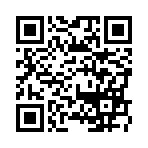2010年04月24日
小論文「『市民金融』で躍動するまちづくりを目指す」
社団法人建設コンサルタンツ協会主催 懸賞論文「低炭素社会にふさわしいまちづくり」(2010年9月末締め切り) 応募作
「市民金融」で躍動するまちづくりを目指す
山本泰弘(筑波大学大学院 人文社会科学研究科 科目等履修生)
山本泰弘(筑波大学大学院 人文社会科学研究科 科目等履修生)
<低炭素社会への「投資」の必要性>
環境問題を"考える"ことのみに豊富な時を費やせる時代は終わった。
現代我々は、環境・エネルギー面はもちろん、交通や人口変動、その他既存の都市・町村が抱える課題を乗り越えた、より快適で豊かな社会の建設を行うべき時に来ている。
その先導役として、当地つくばの国立環境研究所をはじめとする研究機関が、実現可能な「低炭素社会」ビジョンを掲げている。低環境負荷で高エネルギー効率、化石燃料への依存から脱却して再生可能エネルギーのシェアを伸ばし、それでいて人々がより豊かな暮らしを営める社会の展望が、現実的なゴールとして研究者の手により描かれているのである。
これに対応して、政府は2008年より「環境モデル都市構想」を開始し、環境都市の実現の模範となる先進的な自治体の取り組みを支援しつつある。他方、東京大学・千葉大学が参画する「柏の葉キャンパスタウン構想」のように、公(市・県)・民(企業・市民)・学(大学)連携による「サステイナビリティ」をキーワードとした都市開発の実践も進んでいる。
これら先端的な研究や開発事業の成果を見れば未来の展望は明るいように思えるが、現状「低炭素社会」のビジョンを実現に結びつけられるのは、条件に恵まれたごく一部の地域にとどまると言わざるを得ない。低炭素社会を建設するためには、決して少額では済まない「投資」が必要なのである。
高度経済成長期の日本は、潤沢な税収と旺盛な需要拡大の勢いを活用して、官・大企業主導による都市開発が進められてきた。公的資金も含め多方面に資本を投下できる経済的な活力が日本社会にはあり、投資額を回収し再投資を行って余りある成果が挙がっていたのである。その帰結として、今の日本の都市ができあがった。
低炭素社会の建設にも投資が必要なのは同様である。英国のスターン・レビューや近年のエコポイント制度が示すごとく、環境対応には「早期に初期投資を行い、効率化によって長期間ランニングコストを軽減すること」が望まれている。太陽光発電設備に始まり、公共交通システム、省エネ住宅・ビル、スマートグリッドなど低炭素社会を構成する要素の一つ一つにそれは当てはまる。そしてこの投資事業は、条件に恵まれた地域のみならず日本全国で、今後約一世代余り(目標年次を2050年と考えて、2010年から40年先)の間に進めていく必要があるのである。
<「市民金融」の生起>
では、今の日本にその十分な担い手はいるのか。
優良企業の世界的な活躍はあるものの日本全体の経済の活力は全盛期より大きく後退し、民間企業は慎重さを極めた経営を迫られ続けている。他方国家・地方財政は、債務の累積と増え続ける社会保障需要に、合理化と緊縮が要求され続けている。低炭素社会への初期投資の供給源を、従来のように全面的にこれらの主体に頼るとすればまさに逆境である。
このような公共投資の財源論を語る上で、かねてよりその活用が期待されてきたものがある。約1,400兆円を超えるとも言われる国民の金融資産である。「投資・資産運用ブーム」が訪れた際に、あるいは金融経済活性化が論じられる際にこの集合的資産の動向が期待され、あるいはそれを呼び込むためのビジネスモデルが練られてきた。しかし積極的な個人資産運用の普及は未だ限定的なものであり、一般の国民にとって身近なものとはなっていないように見える。"眠れる資産"を"生き金"にすることが、依然として日本の課題と言えよう。
これら投資の需給双方の課題を乗り越え、各地域で低炭素社会建設の原資を生み出し、その実現に向けた事業を興していく必要がある。その解決策として実績を挙げ始めているのが、「市民金融」である。
これには多様な形態があるが、総称すれば「再生可能エネルギー設備の導入など、地域の公益的事業を実現することを目的とし、その目的への賛同者(主として地域住民)から出資金を募る仕組み」と言える。事業者は組合や株式会社の形をとり、賛同者から寄せられた出資金をもとに事業を経営し、利益を生む。既存の大企業や公企業ではなく市民有志が自発的に事業体を立ち上げ、金融機関などを介さず個人から直接、特定事業や分野に対し出資を募ることが特徴である。資産運用というテーマには親しみがない人々にとっても、"地域のため・将来のためになることに出資する(かつ、多くの場合出資額以上のお金が返還される)"というのであれば関心を持つことであろう。
その模範的な事例として、長野県飯田市を拠点とする「おひさまエネルギーファンド」の再生可能エネルギー事業を挙げる。
これは国内において草分け的存在となる市民出資事業で、太陽光・自然エネルギー発電事業や省エネ機器導入事業について地域住民や域外の賛同者から出資を募り、成功実績と順調な運用成績を挙げている。自然エネルギー政策の専門家が代表を務める株式会社(金融商品取引業者)の形態をとり、匿名組合契約という形で一口10万円から50万円の出資を募集する。事業者(別会社として存在)はそれを元手に太陽光パネルや小水力発電設備の導入、ESCO事業などを行い、生まれた利益を出資金額に上乗せして5年から15年かけ出資者に分配していくという仕組みである。
ここで注目すべきなのは、この事業が単なるお金のやり取りに終始せず地域の人々と社会に並々ならぬ波及効果をもたらしていることである。この事業により多くの幼稚園の屋根に太陽光パネルが設置され、そこに通う子どもたちの環境教育に活かされているという。子どもに関連する話題は各家庭の話題となり、他にも公民館など公的施設への設備の導入が進むことでその動きは住民の共通認識を強めていく。現在に至ってはこのモデルが飯田市ならではのものとして市民の誇りのようにとらえられている。それと連動するように、飯田市はこの"市民ファンドによる「太陽光市民共同発電」"を柱の一つとして国から「環境モデル都市」の認定を得るに至った。
他方、同事業のウェブサイトで紹介されている「出資者の声」の中には、家族が子・孫の世代のためとして、老夫婦が国や故郷のためとして出資するという事例が見られる。金銭上の利得だけでは人はお金を動かさない。お金を出す側も預かる側も世間にとっても善い「三方善し」の使い方であるからこそ賛同者が集まるのであろう。
また、各地で単一事業を継続的に行い実績を残している市民金融事業の例として、株式会社市民風力発電と各地域の有志団体(NPO法人や有限責任中間法人の形態をとる)による「市民風車」事業がある。前者は市民出資による風力発電事業を専門とするコンサルティング・運用管理業者で、各地域で風車建設を発案し賛同者から出資を募るNPO法人などの委託を受け、その企画・調査から建設・メンテナンスまでを担当する。各地域に拠点を置く有志団体は、専門的な知識や事業管理などをこの事業者に頼り、事業のPRと募債に注力することができる。北海道・東北を中心とした計11基の風車が市民出資によって建設され、この事業者によって管理されているという(2009年4月時点)。地域を対象にした出資募集と、発電設備に関する専門的業務の分業がうまく成り立っている例と言える。
これらの他にも、市民からの出資や企業・団体からの寄附金を元手に、環境分野には限らないが社会的起業や公共財の提供など地域社会を支える活動に資金を融通しようという取り組みが日本各地に散見される。いまだ全国的な広がりとは言えないかもしれないが、従来のように金融機関に一任するものでない、市民各位の意思がより直接的に反映された資金の流れが着実に育ちつつある。
<地域の自立的な「まちづくり」へ>
これら「市民金融」の意味するところは、もはや社会の建設を、行政・大企業に先んじて地域住民有志が指揮・率先すべき時が来ているということである。従来、社会の建設について住民が行うことといえば、おカミたる自治体に"請願・陳情"したり、有力企業を"誘致"したりすることが主流であった。主体を他に求めることができていたのである。それが今変化を迫られている。徐々にではあろうが、住民有志・地元企業有志が立案し地域内外の賛同者が出資して 来るべき社会へのステップとなるプロジェクトを実行する――というあり方が存在感を増すのが必要とされる。
もちろん、市民金融には制度上の障害・認知度不足・規模の限界などという課題が山積みの状況にある。環境省がこのテーマに着手しており、モデル事業を選定して補助金※を出すなど市民金融の動きを促進する事業を行っているが、規模や影響力の点でささやかなものであり、政府としての大胆な注力が望まれる。現在は多様な障害をかいくぐる形で限定的な実践例が挙がっていると言えるが、制度の整備や 既存事例があることによる認知度の向上に伴い、市民金融(事業)の量的・質的発展が実現するのではないか。事業を支援するコンサルティング会社・シンクタンクも出現するだろうし、あるいは「株式会社市民風力発電」のような専門業務担当事業者も多分野で出現する余地がある。金融事業に関するノウハウやリスク管理といった面で、地域金融機関との有機的な連携も期待される。
市民金融には、「金融資産の地産地消」という観点も含まれる。預金者が金融機関にお金を預けているだけでは必ずしも地域にその資金が巡るわけではなく、預金の使途も実感しにくいが、地域のためのプロジェクトに直接出資するとなれば、資金は域内で循環することになり自分のお金の使われ方も見守れる。同時に、政府出資のいわゆる公共事業ではない形の雇用創出ともなりうる。
従来型の「資産運用」ならば、経済的な利益のみが注視されリターンの大きい運用方法がよしとされるであろう。しかし市民金融は別の価値基準を提示してくれる。"社会作りの一端に参加した"という意識や"みんなの力でこれができた"という感慨のような、いわば地域への「縁」である。日本古来の「結」の現代版とも言えるかもしれない。遠隔地から出資したという人の中には、その地域に縁を感じて実際に訪れる人もいると聞く。
<市民金融を通して発展する地域像のために>
以上総じて、私が「低炭素社会にふさわしいまちづくり」として描くのは、市民金融の仕組みが成り立って各地域での自律的な低炭素社会づくりが進んでいくあり方である。原動力となるのは、その仕組み以上に低炭素なまちづくりを志向する住民有志・地元企業有志である。専門的知識が万全でなくても、"まちおこしをしたい"・"次世代へ継承できるものを残したい"・"他地域の成功にあやかりたい"などという志をもった者が、手段として市民金融の仕組みをとれるようになる。法制度や支援体制が調えられ、多くの参考事例からノウハウを学ぶことができる。事業の実効性を診断・向上する上では環境コンサルや環境NPOにアクセスでき、実効性が認められる事業については地域金融機関や自治体が募債の促進役になる。住民はもちろん、通勤・通学者、他所に在住するその地域の出身者や、縁あってそこを訪れた人、たまたまその事業が気に入った人など多くの人々が関心をもって進展を見つめている。そこには縁が生まれ、薄らいでいた地域のつながりが新たな形で回復する。
これを理想論に終わらせず、現実に結びつける上での根源的な課題がある。
先に「制度上の障害・認知度不足・規模の限界など」と市民金融が直面する目先の課題を挙げたが、社会の変革の一翼を担う新出のテーマとして、市民金融にはそれに取り組む「人」が重層的に集まる必要があるのではないか。実践者となり第一線で事業に携わる人もそうだが、これをテーマとして情報の集積や調査・研究活動に従事する人の層はまだまだ薄いように思われる。低炭素社会を構成する次世代エネルギーシステムや各種機器に採用される環境技術などの"骨組み・部品"については広範囲で先端的な研究開発活動が進められているが、その社会を実現するプロセスとしての金融形態・ビジネスモデル・政策については「知」の形成より不確実性を負った実践が先立っているのではないか。
「世界に誇る日本の技術力」とはよく言われるが、低炭素社会にふさわしいまちづくりやひいては日本の低炭素社会政策に真に必要とされているのはこちらの「プロセス」のほうである。経済力をはじめ、限られた資源をいかに活用することが合理的なまちづくり・社会づくりへの最適解なのか、いかにすれば人々や企業・自治体などの主体を適材適所に快く参画させられるのか――これを研究し弁えた人材が各地のまちづくり・日本の社会づくりの中核にあるのが望ましい。
市民金融というテーマはすべての人々が無縁ではありえない「お金」・「地域」に焦点を当てているだけに、恰好の「プロセス」と言える。社会の諸アクターが(損をせず)互いに協調して低炭素なまちづくりを継続していけるかという課題。これは一か八かの勝負として踏み込むべきものではなく、成功の条件を知る水先案内人の存在が要るものである。
地域の自主性や活力を引き出すための国レベルの制度論としては、長年にわたり道州制が議論の俎上にある。しかし巨視的な制度・枠組みの改革も重要であろうが、地域の健全な生存や、低炭素化も含む発展をなす上で実質的に必要なのは、各地の人・お金・風土や特性 を活かして事業を興すことではないだろうか。いわゆる「起業ブーム」・「投資ブーム」は去ったとされ起業件数も少なくなったと言われるが、金儲けだけが目的ではない起業・創業と、それを支援しようとする投資は途絶えることはないだろう。人々が流行に乗ってお金を操ろうとした時代の反省を踏まえ、”自分の経済的利益だけのため”ではなく”自分や家族も含む地域の、経済・環境・社会的利益(=公益)のため”、”一攫千金”ではなく”長期にわたり安定的な利益を得る”ことを目的とした投資が志向されているのだ。また若者や都市からの移住者が地方で独立しその地域に溶け込んだ暮らしを送ろうとするケースも少なからず見られる。農業や喫茶店のようなものでも起業であることには変わらないから、いまだ起業を夢見る人や地域密着型の暮らしを送りたい人はいるはずなのである。
だから例えば、市民金融による事業を行いやすくする制度を他地域に先駆けて調えた自治体があったとすれば、域内で投資の流れが起こるというだけでなく、外部からも投資がもたらされたり、起業の志を持つ者が移り住んだり、波及経済効果があったりと多様な付加的効果を得ることになるかもしれない。またこれにより前述事例のごとく目に見える形で低炭素化事業が行われていけば、住環境・教育環境としても人気を得て移住者を引き寄せることになるとも考えられる。
経済活動にとどまらず、まちづくりの血液でもあるお金。低炭素社会というテーマを試金石に、これを地域主導でうまく循環させられるかどうかが、今後質的に持続発展する地域と衰退する地域とを分けることになるのではないか。
<参考文献>
*環境モデル都市構想~未来へのまちづくり~:
(内閣官房 低炭素都市推進協議会 によるWebサイト)
http://ecomodelproject.go.jp/
*柏市役所 柏の葉国際キャンパスタウン構想:
(千葉県柏市役所によるWebサイト)
http://www.city.kashiwa.lg.jp/notice/kashiwanoha_campus/top.htm
*国際キャンパスタウン構想とは|柏の葉キャンパスシティプロジェクト|三井不動産:
(三井不動産株式会社によるWebサイト)
http://www.mitsuifudosan.co.jp/kashiwanoha/kokusai_campustown/index.html
*大西隆、小林光 編著『低炭素都市 ―これからのまちづくり』学芸出版社、2010年。
*国際比較:個人金融資産1,400兆円:日本銀行:
(日本銀行によるWebサイト)
http://www.boj.or.jp/type/exp/seisaku/exphikaku.htm
・環境モデル都市・飯田
http://www.ecomodel-iida.com/
・ENERGY GREEN グリーン電力証書 - ENERGY GREENとは
http://www.energygreen.co.jp/about_ohisama.htm
・おひさまエネルギーファンド株式会社
http://www.ohisama-fund.jp/
環境問題を"考える"ことのみに豊富な時を費やせる時代は終わった。
現代我々は、環境・エネルギー面はもちろん、交通や人口変動、その他既存の都市・町村が抱える課題を乗り越えた、より快適で豊かな社会の建設を行うべき時に来ている。
その先導役として、当地つくばの国立環境研究所をはじめとする研究機関が、実現可能な「低炭素社会」ビジョンを掲げている。低環境負荷で高エネルギー効率、化石燃料への依存から脱却して再生可能エネルギーのシェアを伸ばし、それでいて人々がより豊かな暮らしを営める社会の展望が、現実的なゴールとして研究者の手により描かれているのである。
これに対応して、政府は2008年より「環境モデル都市構想」を開始し、環境都市の実現の模範となる先進的な自治体の取り組みを支援しつつある。他方、東京大学・千葉大学が参画する「柏の葉キャンパスタウン構想」のように、公(市・県)・民(企業・市民)・学(大学)連携による「サステイナビリティ」をキーワードとした都市開発の実践も進んでいる。
これら先端的な研究や開発事業の成果を見れば未来の展望は明るいように思えるが、現状「低炭素社会」のビジョンを実現に結びつけられるのは、条件に恵まれたごく一部の地域にとどまると言わざるを得ない。低炭素社会を建設するためには、決して少額では済まない「投資」が必要なのである。
高度経済成長期の日本は、潤沢な税収と旺盛な需要拡大の勢いを活用して、官・大企業主導による都市開発が進められてきた。公的資金も含め多方面に資本を投下できる経済的な活力が日本社会にはあり、投資額を回収し再投資を行って余りある成果が挙がっていたのである。その帰結として、今の日本の都市ができあがった。
低炭素社会の建設にも投資が必要なのは同様である。英国のスターン・レビューや近年のエコポイント制度が示すごとく、環境対応には「早期に初期投資を行い、効率化によって長期間ランニングコストを軽減すること」が望まれている。太陽光発電設備に始まり、公共交通システム、省エネ住宅・ビル、スマートグリッドなど低炭素社会を構成する要素の一つ一つにそれは当てはまる。そしてこの投資事業は、条件に恵まれた地域のみならず日本全国で、今後約一世代余り(目標年次を2050年と考えて、2010年から40年先)の間に進めていく必要があるのである。
<「市民金融」の生起>
では、今の日本にその十分な担い手はいるのか。
優良企業の世界的な活躍はあるものの日本全体の経済の活力は全盛期より大きく後退し、民間企業は慎重さを極めた経営を迫られ続けている。他方国家・地方財政は、債務の累積と増え続ける社会保障需要に、合理化と緊縮が要求され続けている。低炭素社会への初期投資の供給源を、従来のように全面的にこれらの主体に頼るとすればまさに逆境である。
このような公共投資の財源論を語る上で、かねてよりその活用が期待されてきたものがある。約1,400兆円を超えるとも言われる国民の金融資産である。「投資・資産運用ブーム」が訪れた際に、あるいは金融経済活性化が論じられる際にこの集合的資産の動向が期待され、あるいはそれを呼び込むためのビジネスモデルが練られてきた。しかし積極的な個人資産運用の普及は未だ限定的なものであり、一般の国民にとって身近なものとはなっていないように見える。"眠れる資産"を"生き金"にすることが、依然として日本の課題と言えよう。
これら投資の需給双方の課題を乗り越え、各地域で低炭素社会建設の原資を生み出し、その実現に向けた事業を興していく必要がある。その解決策として実績を挙げ始めているのが、「市民金融」である。
これには多様な形態があるが、総称すれば「再生可能エネルギー設備の導入など、地域の公益的事業を実現することを目的とし、その目的への賛同者(主として地域住民)から出資金を募る仕組み」と言える。事業者は組合や株式会社の形をとり、賛同者から寄せられた出資金をもとに事業を経営し、利益を生む。既存の大企業や公企業ではなく市民有志が自発的に事業体を立ち上げ、金融機関などを介さず個人から直接、特定事業や分野に対し出資を募ることが特徴である。資産運用というテーマには親しみがない人々にとっても、"地域のため・将来のためになることに出資する(かつ、多くの場合出資額以上のお金が返還される)"というのであれば関心を持つことであろう。
その模範的な事例として、長野県飯田市を拠点とする「おひさまエネルギーファンド」の再生可能エネルギー事業を挙げる。
これは国内において草分け的存在となる市民出資事業で、太陽光・自然エネルギー発電事業や省エネ機器導入事業について地域住民や域外の賛同者から出資を募り、成功実績と順調な運用成績を挙げている。自然エネルギー政策の専門家が代表を務める株式会社(金融商品取引業者)の形態をとり、匿名組合契約という形で一口10万円から50万円の出資を募集する。事業者(別会社として存在)はそれを元手に太陽光パネルや小水力発電設備の導入、ESCO事業などを行い、生まれた利益を出資金額に上乗せして5年から15年かけ出資者に分配していくという仕組みである。
ここで注目すべきなのは、この事業が単なるお金のやり取りに終始せず地域の人々と社会に並々ならぬ波及効果をもたらしていることである。この事業により多くの幼稚園の屋根に太陽光パネルが設置され、そこに通う子どもたちの環境教育に活かされているという。子どもに関連する話題は各家庭の話題となり、他にも公民館など公的施設への設備の導入が進むことでその動きは住民の共通認識を強めていく。現在に至ってはこのモデルが飯田市ならではのものとして市民の誇りのようにとらえられている。それと連動するように、飯田市はこの"市民ファンドによる「太陽光市民共同発電」"を柱の一つとして国から「環境モデル都市」の認定を得るに至った。
他方、同事業のウェブサイトで紹介されている「出資者の声」の中には、家族が子・孫の世代のためとして、老夫婦が国や故郷のためとして出資するという事例が見られる。金銭上の利得だけでは人はお金を動かさない。お金を出す側も預かる側も世間にとっても善い「三方善し」の使い方であるからこそ賛同者が集まるのであろう。
また、各地で単一事業を継続的に行い実績を残している市民金融事業の例として、株式会社市民風力発電と各地域の有志団体(NPO法人や有限責任中間法人の形態をとる)による「市民風車」事業がある。前者は市民出資による風力発電事業を専門とするコンサルティング・運用管理業者で、各地域で風車建設を発案し賛同者から出資を募るNPO法人などの委託を受け、その企画・調査から建設・メンテナンスまでを担当する。各地域に拠点を置く有志団体は、専門的な知識や事業管理などをこの事業者に頼り、事業のPRと募債に注力することができる。北海道・東北を中心とした計11基の風車が市民出資によって建設され、この事業者によって管理されているという(2009年4月時点)。地域を対象にした出資募集と、発電設備に関する専門的業務の分業がうまく成り立っている例と言える。
これらの他にも、市民からの出資や企業・団体からの寄附金を元手に、環境分野には限らないが社会的起業や公共財の提供など地域社会を支える活動に資金を融通しようという取り組みが日本各地に散見される。いまだ全国的な広がりとは言えないかもしれないが、従来のように金融機関に一任するものでない、市民各位の意思がより直接的に反映された資金の流れが着実に育ちつつある。
<地域の自立的な「まちづくり」へ>
これら「市民金融」の意味するところは、もはや社会の建設を、行政・大企業に先んじて地域住民有志が指揮・率先すべき時が来ているということである。従来、社会の建設について住民が行うことといえば、おカミたる自治体に"請願・陳情"したり、有力企業を"誘致"したりすることが主流であった。主体を他に求めることができていたのである。それが今変化を迫られている。徐々にではあろうが、住民有志・地元企業有志が立案し地域内外の賛同者が出資して 来るべき社会へのステップとなるプロジェクトを実行する――というあり方が存在感を増すのが必要とされる。
もちろん、市民金融には制度上の障害・認知度不足・規模の限界などという課題が山積みの状況にある。環境省がこのテーマに着手しており、モデル事業を選定して補助金※を出すなど市民金融の動きを促進する事業を行っているが、規模や影響力の点でささやかなものであり、政府としての大胆な注力が望まれる。現在は多様な障害をかいくぐる形で限定的な実践例が挙がっていると言えるが、制度の整備や 既存事例があることによる認知度の向上に伴い、市民金融(事業)の量的・質的発展が実現するのではないか。事業を支援するコンサルティング会社・シンクタンクも出現するだろうし、あるいは「株式会社市民風力発電」のような専門業務担当事業者も多分野で出現する余地がある。金融事業に関するノウハウやリスク管理といった面で、地域金融機関との有機的な連携も期待される。
市民金融には、「金融資産の地産地消」という観点も含まれる。預金者が金融機関にお金を預けているだけでは必ずしも地域にその資金が巡るわけではなく、預金の使途も実感しにくいが、地域のためのプロジェクトに直接出資するとなれば、資金は域内で循環することになり自分のお金の使われ方も見守れる。同時に、政府出資のいわゆる公共事業ではない形の雇用創出ともなりうる。
従来型の「資産運用」ならば、経済的な利益のみが注視されリターンの大きい運用方法がよしとされるであろう。しかし市民金融は別の価値基準を提示してくれる。"社会作りの一端に参加した"という意識や"みんなの力でこれができた"という感慨のような、いわば地域への「縁」である。日本古来の「結」の現代版とも言えるかもしれない。遠隔地から出資したという人の中には、その地域に縁を感じて実際に訪れる人もいると聞く。
<市民金融を通して発展する地域像のために>
以上総じて、私が「低炭素社会にふさわしいまちづくり」として描くのは、市民金融の仕組みが成り立って各地域での自律的な低炭素社会づくりが進んでいくあり方である。原動力となるのは、その仕組み以上に低炭素なまちづくりを志向する住民有志・地元企業有志である。専門的知識が万全でなくても、"まちおこしをしたい"・"次世代へ継承できるものを残したい"・"他地域の成功にあやかりたい"などという志をもった者が、手段として市民金融の仕組みをとれるようになる。法制度や支援体制が調えられ、多くの参考事例からノウハウを学ぶことができる。事業の実効性を診断・向上する上では環境コンサルや環境NPOにアクセスでき、実効性が認められる事業については地域金融機関や自治体が募債の促進役になる。住民はもちろん、通勤・通学者、他所に在住するその地域の出身者や、縁あってそこを訪れた人、たまたまその事業が気に入った人など多くの人々が関心をもって進展を見つめている。そこには縁が生まれ、薄らいでいた地域のつながりが新たな形で回復する。
これを理想論に終わらせず、現実に結びつける上での根源的な課題がある。
先に「制度上の障害・認知度不足・規模の限界など」と市民金融が直面する目先の課題を挙げたが、社会の変革の一翼を担う新出のテーマとして、市民金融にはそれに取り組む「人」が重層的に集まる必要があるのではないか。実践者となり第一線で事業に携わる人もそうだが、これをテーマとして情報の集積や調査・研究活動に従事する人の層はまだまだ薄いように思われる。低炭素社会を構成する次世代エネルギーシステムや各種機器に採用される環境技術などの"骨組み・部品"については広範囲で先端的な研究開発活動が進められているが、その社会を実現するプロセスとしての金融形態・ビジネスモデル・政策については「知」の形成より不確実性を負った実践が先立っているのではないか。
「世界に誇る日本の技術力」とはよく言われるが、低炭素社会にふさわしいまちづくりやひいては日本の低炭素社会政策に真に必要とされているのはこちらの「プロセス」のほうである。経済力をはじめ、限られた資源をいかに活用することが合理的なまちづくり・社会づくりへの最適解なのか、いかにすれば人々や企業・自治体などの主体を適材適所に快く参画させられるのか――これを研究し弁えた人材が各地のまちづくり・日本の社会づくりの中核にあるのが望ましい。
市民金融というテーマはすべての人々が無縁ではありえない「お金」・「地域」に焦点を当てているだけに、恰好の「プロセス」と言える。社会の諸アクターが(損をせず)互いに協調して低炭素なまちづくりを継続していけるかという課題。これは一か八かの勝負として踏み込むべきものではなく、成功の条件を知る水先案内人の存在が要るものである。
地域の自主性や活力を引き出すための国レベルの制度論としては、長年にわたり道州制が議論の俎上にある。しかし巨視的な制度・枠組みの改革も重要であろうが、地域の健全な生存や、低炭素化も含む発展をなす上で実質的に必要なのは、各地の人・お金・風土や特性 を活かして事業を興すことではないだろうか。いわゆる「起業ブーム」・「投資ブーム」は去ったとされ起業件数も少なくなったと言われるが、金儲けだけが目的ではない起業・創業と、それを支援しようとする投資は途絶えることはないだろう。人々が流行に乗ってお金を操ろうとした時代の反省を踏まえ、”自分の経済的利益だけのため”ではなく”自分や家族も含む地域の、経済・環境・社会的利益(=公益)のため”、”一攫千金”ではなく”長期にわたり安定的な利益を得る”ことを目的とした投資が志向されているのだ。また若者や都市からの移住者が地方で独立しその地域に溶け込んだ暮らしを送ろうとするケースも少なからず見られる。農業や喫茶店のようなものでも起業であることには変わらないから、いまだ起業を夢見る人や地域密着型の暮らしを送りたい人はいるはずなのである。
だから例えば、市民金融による事業を行いやすくする制度を他地域に先駆けて調えた自治体があったとすれば、域内で投資の流れが起こるというだけでなく、外部からも投資がもたらされたり、起業の志を持つ者が移り住んだり、波及経済効果があったりと多様な付加的効果を得ることになるかもしれない。またこれにより前述事例のごとく目に見える形で低炭素化事業が行われていけば、住環境・教育環境としても人気を得て移住者を引き寄せることになるとも考えられる。
経済活動にとどまらず、まちづくりの血液でもあるお金。低炭素社会というテーマを試金石に、これを地域主導でうまく循環させられるかどうかが、今後質的に持続発展する地域と衰退する地域とを分けることになるのではないか。
<参考文献>
*環境モデル都市構想~未来へのまちづくり~:
(内閣官房 低炭素都市推進協議会 によるWebサイト)
http://ecomodelproject.go.jp/
*柏市役所 柏の葉国際キャンパスタウン構想:
(千葉県柏市役所によるWebサイト)
http://www.city.kashiwa.lg.jp/notice/kashiwanoha_campus/top.htm
*国際キャンパスタウン構想とは|柏の葉キャンパスシティプロジェクト|三井不動産:
(三井不動産株式会社によるWebサイト)
http://www.mitsuifudosan.co.jp/kashiwanoha/kokusai_campustown/index.html
*大西隆、小林光 編著『低炭素都市 ―これからのまちづくり』学芸出版社、2010年。
*国際比較:個人金融資産1,400兆円:日本銀行:
(日本銀行によるWebサイト)
http://www.boj.or.jp/type/exp/seisaku/exphikaku.htm
・環境モデル都市・飯田
http://www.ecomodel-iida.com/
・ENERGY GREEN グリーン電力証書 - ENERGY GREENとは
http://www.energygreen.co.jp/about_ohisama.htm
・おひさまエネルギーファンド株式会社
http://www.ohisama-fund.jp/
2012-11 プライマリ・ケア+αの広場「健こう民館」構想
2014年12月:復興庁主催政策コンテスト「REVIVE JAPAN CUP」入選・決選進出!
地球温暖化対策の中期目標に対するコメント(麻生政権時)
小論文 「商業立国 日本」【3.三つの提言】
小論文 「商業立国 日本」【2.日本伝統の商業倫理】
小論文 「商業立国 日本」【1.本当の「商業」はどこへ】
2014年12月:復興庁主催政策コンテスト「REVIVE JAPAN CUP」入選・決選進出!
地球温暖化対策の中期目標に対するコメント(麻生政権時)
小論文 「商業立国 日本」【3.三つの提言】
小論文 「商業立国 日本」【2.日本伝統の商業倫理】
小論文 「商業立国 日本」【1.本当の「商業」はどこへ】
Posted by 山本泰弘 at 03:00│Comments(0)
│【応募・投稿】
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。